|
|
「ひかりoneホーム ギガ得プラン」の本当のインパクト昨年秋KDDIが戸建向けの1GbpsのFTTHサービスを「ひかりoneホーム ギガ得プラン」としてスタートした。Radish Network Speed Testingは100Mbps以上を測定できる数少ない測定サイトであることもあり、「ギガ得プラン」はサービス開始直後からかなりの測定の利用があった。そこで、十分と言えるデータがそろってきたところで、少し冷静に「ひかりoneホーム ギガ得プラン」の本当の意味について考察してみたいと思う。
■想像以上に良好な速度「ギガ得プラン」のセールスポイントは低価格での1GbpsFTTHサービスであり、ベストエフォート型のサービスとしての質に疑問の声が多かったように思う。
ニュースリリースでの別紙に記載された「連続的かつ大量の通信をご利用される一部のお客さまについて、ネットワーク資源の品質・公平性確保を目的とした通信利用の制限を実施する場合があります。」という文言も1Gbpsが十分享受できないサービスなのではという憶測を呼んでいた。正直、筆者もサービス開始までそのように予想した一人だ。しかし、実際の結果は予想をはるかに上回る良好なものだった。
実際の利用者の測定データは、測定者が公開したものを「みんなの測定結果」で閲覧することができる。
[測定結果例]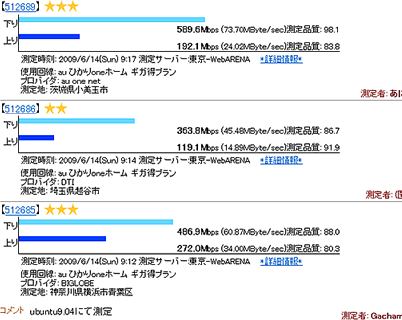
実際の測定結果では700Mbpsを超えるような値もみられる。東京の測定サーバーは内部での転送試験でも850Mbpsが限界で、サーバーの稼働状況から判断してある程度安定的な測定ができる速度は500Mbps程度なのだが、すでに測定サーバー側の限界に近い速度になっていることが分かる。
測定者全体の速度分布は図のようになる。
[ギガ得分布図]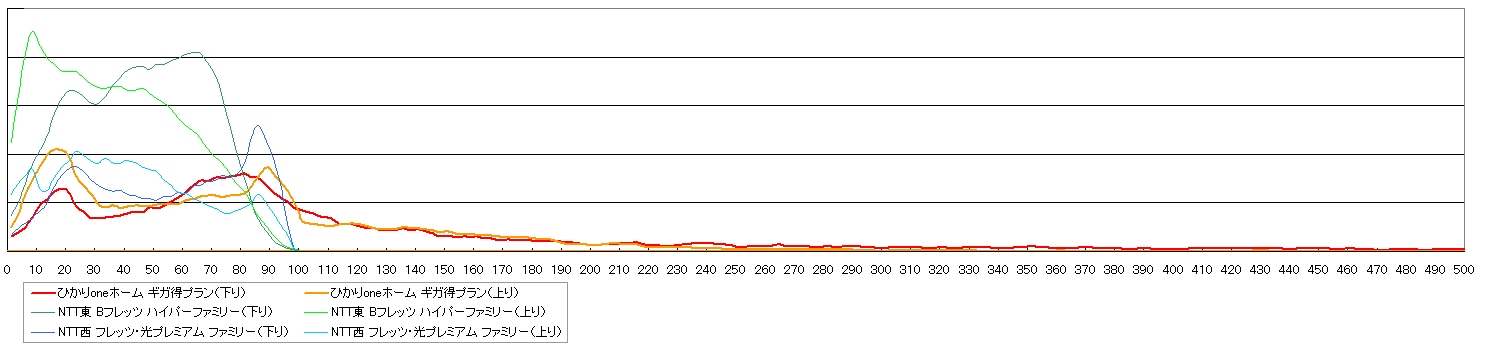 ※縦軸は分布強度を表しています。各集計対象に対して標準化しており、集計対象間のサンプル数をリニアに反映するものではありません。
※データは2009年1月〜3月にRadish Network Speed Testing (WebARENA版 東京サーバー)で測定されたものです。測定品質80未満、および同一測定者による測定値は除く。
測定者全体の速度分布をみると、1Gbpsというサービスの割りにあまり良い速度が出ていないような印象を受けるかもしれないが、例えば最近のSATA2のHDDのシーケンシャルなアクセスでも1Gbps程度の速度であり、1Gbpsという速度は測定者のPC自体の限界もかなり影響してくる領域になっている。例えば100Mbpsの回線が提供され始めた頃は、その速度を処理できるPCやルーターは少なく回線の能力を使いきれていないことが多かった。
■あまり注目されていない料金設定今回関東地方で初めての本格的な個人向け1Gbpsサービスの開始ということで、ブロードバンドの進歩という視点からその速度ばかりが注目されがちだが、「ひかりoneホーム ギガ得プラン」のもう一つの大きなポイントはその価格設定だ。あまり取り上げられていないように思うが、2年ごとの契約更新という、携帯電話などによくある制限があるものの既存の100Mbpsのサービスよりも価格を下げてのサービスインとなった。速度が向上して月々1000円強の値下げとなっている。
携帯電話は引っ越し先などでもそのまま使えるのに対して、引っ越しなどの利用者側が解約日をコントロールしにくい固定回線に“2年ごとの契約更新でそれ以外のタイミングでは解約料をとる”という携帯電話のスタイルはあまりなじまないように思うが、解約料は9,975円で9ヶ月以上の利用で従来のプランより得になることになる。
“2年ごとの契約更新”は契約した月から25ヶ月目の1ヶ月間とその後24ヶ月ごとの1ヶ月間は解約料なしに解約できるそうだ。ただし、上手くこの期間に解約するためには色々と気を付けることもあるようなので、解約料なしの解約を望む場合は、あらかじめサポートに問い合わせて段取りを確認しておいたほうが良いかもしれない。個人的には解約料があっても良いと思うが、もう少し分かりやすいほうが気持ちがいいのではと思う。
NTT東西のメインストリームの一戸建て向けサービス(0AB〜J番号のIP電話込み)と「ひかりoneホーム ギガ得プラン」を価格面で比較してみた。
割引などを考慮すると価格差は僅差だが他社の100Mbpsのサービスと同等かそれより低価格でのサービスなことが分かる。
価格表
※価格は2009/3/23現在、ISPは調査時点での累積コストの低いものを選択した。割引の変動は大きいので最新の価格は価格comのブロードバンド料金比較等でご確認ください。
※ユニバーサルサービス料(8.4円/月・契約電話番号)別
5年間の累積コストのグラフ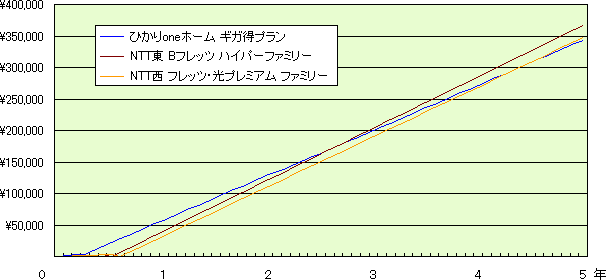
■帯域制限なしの時代への突入今までの多くのサービスは利用可能な帯域にあわせて価格設定がされてきた。しかし「ひかりoneホーム ギガ得プラン」は普及価格帯で一気に回線の能力の上限までを無制限に利用可能にしている。これは、有線接続のネットワークが帯域制限なしの時代に突入したことをあらわしているのではないだろうか。
例えば以前のISPのサービスではメールボックスとして使用できるディスクスペースを容量に応じて細かく価格設定していた時代があった。しかし、現在は実質容量無制限となるようなサービスが普通になっている。これは裏返せばその容量をユーザーが使いきれることはないという事実をあらわしている。
1Gbpsのサービスでも同じことである。帯域幅が非常に広くなってもユーザー側のニーズとしての通信量がすでにある程度飽和しているということだ。例えばStudio Radishのこの速度測定システムは、Webサービスとしてはかなり大きなトラフィックを生むサービスだが、それでも平均した通信量は数十Mbpsだ。サーバー側のニーズでもこの程度なのだから、一般のユーザーがこのような通信量を生み出すことはほとんどないといっていい。しかし、必要な通信量が少ないから1Gbpsは必要ないという議論にはならない。大きなサイズのデータのやり取りでは必要な時間が大幅に短縮される。通信経路から見れば瞬間的には大きな帯域が占有されるが占有されている時間は非常に短くなるということになる。
ムーアの法則という言葉をご存知の方は多いのではないだろうか。テクノロジーの進歩によりCPUの性能はおよそ18ヶ月で倍になり同じ性能なら半分のコストになるというものだ。同じような法則はいくつかあるが、ネットワーク通信分野でもビル・ジョイの法則という法則がある。
ビル・ジョイの法則によれば、ネットワークの性能はおよそ12ヶ月で倍になり、通信量あたりのコストは12ヶ月で半分になる。
そもそも人間が扱える情報量には限りがあり、おのずと必要な通信量にも限界が出てくる。それでもコンピュータの力を借りればより多くの情報を扱うことができるようになるだろう。しかし、ビル・ジョイの法則はムーアの法則を凌駕しており、PCの処理能力比でも通信コストは3年で半分になっていくことになる。必要なトラフィックに対するコストは限りなく下がっていくことになるのだ。残るものは物理的なネットワーク網の維持コストだけになる。定額制の帯域制限なしの時代がやってくるのは必然的な流れといえる。
■エリアの拡大速度がカギかしかし、いくら必然的な流れとしての1Gbpsの出現とはいえ、このタイミングでの普及価格帯での実質的な帯域制限なしはかなりのインパクトを感じる。個人的にはかつて旋風を巻き起こした「Yahoo! BB」が登場したときのようなインパクトを感じる。
にもかかわらず「Yahoo! BB」の当時の熱気のようなものはない。派手なプロモーション活動をしていないという違いもあるかもしれないが、根本的にはエリアの拡大速度がカギのように思う。当時は手ごろなブロードバンドがもうすぐ自宅もサービスエリアに入るのではとワクワクするくらいのスピード感があった。FTTHはサービスを開始するのに手間のかかるインフラだが、NTTを圧倒するようなスピード感が出てくれば爆発するようなポテンシャルがあるのではないだろうか。
導入の手軽さが待たれるFTTH根本的にFTTH全体として普及にスピード感がない。これはエリアの拡大速度以外にも引き込み自体の大変さも起因しているのではないだろうか。
ADSLのように、申し込んで、モデムが届き、繋ぐだけ、というのとは明らかに手軽さが違う。特に借り住まいの場合などはこの辺は大きな障壁となる。全国の平均的な持ち家率は60%程度だが、エリアとして開拓されている都市部では低くなる傾向があり、例えば東京都では40%まで下がる。加えて需要の多い若い世代になるとさらに持ち家率は下がる。借り住まいの中でも特にマンションタイプのターゲットにならないような小規模のアパートはFTTHの蚊帳の外の状態だ。こう考えると現在エリア内の住人で利用したい気持ちがあってもそう簡単にはFTTHを導入できないユーザーが相当数はいるのではないかと想像される。
こうした点では無線LANやHomePNA、PLCなどいろいろなアイディアがあるが、ある程度普及した一般的な手法が望まれる。そもそも持ち家であっても、取り回しの悪い光ケーブルを部屋の中まで引き回すのはいかにも不便だ。
現在筆者はフレッツを使用しているがひかりoneにキャリアを変えようと思ったら(残念ながらエリア外なのだが)屋内まで工事が必要になってくる。例えばLANの給電(IEEE802.3af)を使用してOUNを屋外に掃き出し、OUNにはCUTから給電するようなスタイルも考えられるのではないだろうか。この辺がある程度規格化されてくれればラインの両端の機器を取り替えるだけにできるはずだ。こうしたものこそ国が積極的にある程度絞って規格化を促し、キャリア間の競争を促す政策が必要のように思う。競争も起こるが、色々とコストも下がるだろうし市場規模も大きくなるだろう。
Ryuji K. 2009/07/01
※この記事は2009年1月〜3月にRadish Network Speed Testing (WebARENA版 東京サーバー)で測定されたデータを元に執筆しております。データそれぞれに引用日を記載している場合もありますのでご注意ください。「みんなの測定結果」のリンク先については、最新データとなっております。
・関連サイト auの光ファイバーサービス「ひかりone」
|
広告 by AdSense
雑誌等への転載について
統計データの転載に関するお問い合わせはメールにて受け付けております。
統計処理の形式に関するご要望もご相談ください。
当サイトはリンクフリーです 
https://www.studio-radish.com Studio Radish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||